オサカナ小ネタ
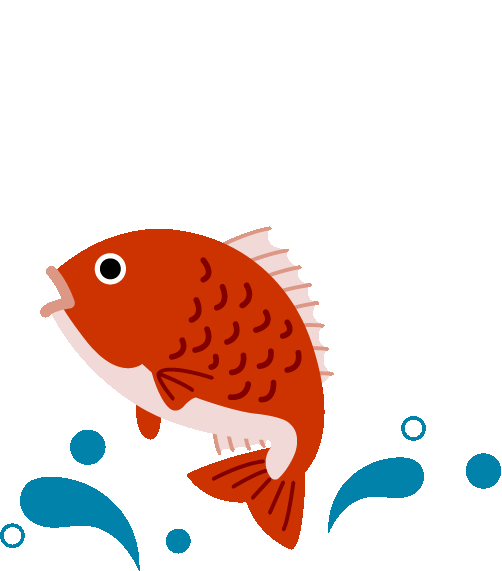
「サカナハメグル」の第六弾を公開しました。今回は、静岡県熱海市の網代漁港を紹介します。深海が近く天然の良港として知られる網代漁港。定置網で獲れたアジやキンメなどの鮮魚は、温泉宿で多彩な料理に生まれ変わり、旅の味覚を彩ります。ぜひお楽しみください。
サカナハメグル
漁港の活気、市場の熱気。日本各地の漁港や市場を巡り、その土地の文化や漁食を紹介します。海と人々の暮らしがある風景、地域ならではの魚介類や料理。魚を通して、日本の魅力を再発見しましょう。
ナカのひとびと
水産卸業関係者、周辺産業、流通業者、外食事業者など、「うまい魚」の流通に関わるプロたちが集結し、「おいしい魚」について語る場です。業界の裏話や豆知識など、ちょっと通な話題をお楽しみください。







